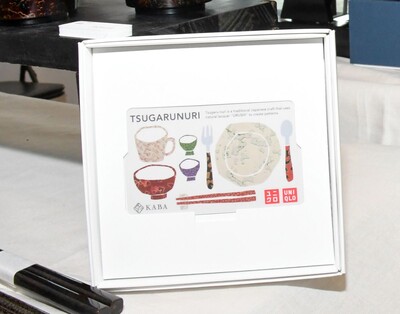弘前市立郷土文学館の文学散歩「今官一生誕の地を歩く」が25日、青森県弘前市内で行われた。
今は1909(明治42)年に弘前で生まれ、今年が生誕110年目。56(昭和31)年に作品集「壁の花」で青森県初の直木賞受賞者となった。
同館企画研究専門官の櫛引洋一さんの案内で同館をスタート。市立図書館前にある今の文学碑「花まぼろしの世に在らば 世も幻の花ならん」や、藤田記念庭園前にある同市出身の先輩詩人一戸謙三の碑などに立ち寄りながら、生家で禅林街の寺院蘭庭院まで歩いた。
櫛引さんは、今が好んで色紙にも書いた「花まぼろしの…」について「生家が禅宗の寺だったことが大きく影響しており、まさに禅の言葉のよう」と述べ、目に見えるものよりも心で見たものを大切にした今の姿勢について解説した。
「津軽を否定する文学」を目指しながら、最期は郷土への感謝の言葉を残したことなどを紹介。風土に頼るだけの文学を嫌いながらも、孤高の創作活動を続け津軽のじょっぱりを地でいった今の根底にあった、郷里への愛情を指摘した。
今は、同年生まれの太宰治と生涯にわたり深い絆で結ばれていたことでも知られ、同文学館では6月20日までスポット企画展「生誕一一〇年 今官一と太宰治の交流」を開催している。
今は1909(明治42)年に弘前で生まれ、今年が生誕110年目。56(昭和31)年に作品集「壁の花」で青森県初の直木賞受賞者となった。
同館企画研究専門官の櫛引洋一さんの案内で同館をスタート。市立図書館前にある今の文学碑「花まぼろしの世に在らば 世も幻の花ならん」や、藤田記念庭園前にある同市出身の先輩詩人一戸謙三の碑などに立ち寄りながら、生家で禅林街の寺院蘭庭院まで歩いた。
櫛引さんは、今が好んで色紙にも書いた「花まぼろしの…」について「生家が禅宗の寺だったことが大きく影響しており、まさに禅の言葉のよう」と述べ、目に見えるものよりも心で見たものを大切にした今の姿勢について解説した。
「津軽を否定する文学」を目指しながら、最期は郷土への感謝の言葉を残したことなどを紹介。風土に頼るだけの文学を嫌いながらも、孤高の創作活動を続け津軽のじょっぱりを地でいった今の根底にあった、郷里への愛情を指摘した。
今は、同年生まれの太宰治と生涯にわたり深い絆で結ばれていたことでも知られ、同文学館では6月20日までスポット企画展「生誕一一〇年 今官一と太宰治の交流」を開催している。