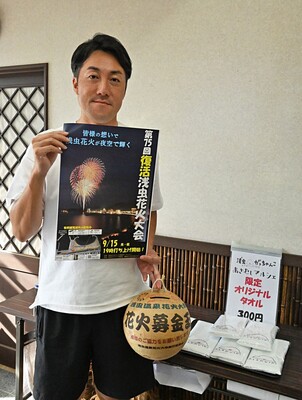青森市の三内丸山遺跡センターは18日から、特別展「縄文時代のおわり-クマとイネと土偶-」を開く。4~6月に行われた特別展「縄文時代のはじまり」に対し、今回は1万年以上続いた縄文時代のうち「終わり」に着目。縄文時代の技術や精神、伝統が残る北日本独特の弥生文化が存在していたことを、出土品などを通じて紹介する。17日は関係者らを招き、内覧会が行われた。10月5日までの開催。
県内を中心に縄文時代晩期から弥生時代前期にかけての土器や土偶などの出土品を展示する。弥生時代前期の砂沢遺跡から出土した土器は、北日本に広がった最後の縄文文化である「亀ケ岡文化」の文様を引き継ぎつつ西日本の弥生前期社会の影響も受けている。
弥生時代前期のクマの形をした土製品は、盛んにクマを表現していた縄文時代の伝統が色濃く残っていたことを示す。
縄文時代に多く使われた赤色顔料も、数は減るが、弥生時代前期にも使われているという。
同センターの坂本雄大所長は「弥生時代の始まりは青森県と西日本とでは違っており、教科書で習う弥生時代とも少し違う。(特別展を通じ)青森県の弥生時代について学んでもらえれば」と語った。
県内を中心に縄文時代晩期から弥生時代前期にかけての土器や土偶などの出土品を展示する。弥生時代前期の砂沢遺跡から出土した土器は、北日本に広がった最後の縄文文化である「亀ケ岡文化」の文様を引き継ぎつつ西日本の弥生前期社会の影響も受けている。
弥生時代前期のクマの形をした土製品は、盛んにクマを表現していた縄文時代の伝統が色濃く残っていたことを示す。
縄文時代に多く使われた赤色顔料も、数は減るが、弥生時代前期にも使われているという。
同センターの坂本雄大所長は「弥生時代の始まりは青森県と西日本とでは違っており、教科書で習う弥生時代とも少し違う。(特別展を通じ)青森県の弥生時代について学んでもらえれば」と語った。