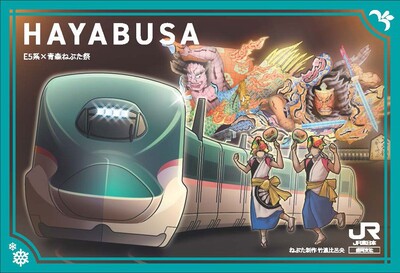江戸時代末期に制作された山車人形「太公望」の衣装と人形本体、装飾品の修復が終了し29日、所蔵する青森県八戸市の龗(おがみ)神社の神楽殿でお披露目された。数年間かけて丁寧に修復が施されており、8月1日の八戸三社大祭の「お通り」と3日の「お還(かえ)り」で、6年ぶりに神社行列に参加する。
人形は高さ143センチ、幅91センチ、奥行き110センチ。胴部に文化9年(1812年)の墨書(ぼくしょ)がある。もう一つの山車人形「武田信玄」と共に2003年、市有形民俗文化財に指定された。
衣装の修復は、八戸三社大祭山車祭り行事保存会が22~24年度、国庫補助を受け事業費約1201万円で実施し、女子美術大学染織文化資源研究所が修理を担当した。生地が破けた上着や、綿が飛び出していたはかまのほか、帽子、帯などを修復した。女子美術大学の大﨑綾子教授(染織文化財保存修復)は「分析したところ、高価な天然染料をふんだんに使っていた。劣化が激しかったが時間をかけ修復した」と説明した。
人形本体は山車祭り行事保存会が22年度、文化庁の補助金を受けて事業費約393万円で、装飾品は龗神社が23年度にそれぞれ修復。いずれも古文化財保存修復研究所(埼玉県)が修理を担当した。このうち本体は台座を新たに制作、心棒を作り直したほか、頭や両腕、両足を修復した。
同研究所役員の長井まみさんは「組み立てる人が作業しやすいよう工夫した。衣装修復の担当者と意思疎通を図りながら人形を修復するという、貴重な体験をさせていただいた」と振り返った。
29日は八戸市教育委員会が市民対象のお披露目会と、神社関係者向けに人形・衣装の取り扱いを学ぶ講習会を開いた。市社会教育課の柏井容子主査兼学芸員は「多くの事業費と時間をかけて修復された。丁寧に取り扱ってほしい」と呼びかけた。
人形は高さ143センチ、幅91センチ、奥行き110センチ。胴部に文化9年(1812年)の墨書(ぼくしょ)がある。もう一つの山車人形「武田信玄」と共に2003年、市有形民俗文化財に指定された。
衣装の修復は、八戸三社大祭山車祭り行事保存会が22~24年度、国庫補助を受け事業費約1201万円で実施し、女子美術大学染織文化資源研究所が修理を担当した。生地が破けた上着や、綿が飛び出していたはかまのほか、帽子、帯などを修復した。女子美術大学の大﨑綾子教授(染織文化財保存修復)は「分析したところ、高価な天然染料をふんだんに使っていた。劣化が激しかったが時間をかけ修復した」と説明した。
人形本体は山車祭り行事保存会が22年度、文化庁の補助金を受けて事業費約393万円で、装飾品は龗神社が23年度にそれぞれ修復。いずれも古文化財保存修復研究所(埼玉県)が修理を担当した。このうち本体は台座を新たに制作、心棒を作り直したほか、頭や両腕、両足を修復した。
同研究所役員の長井まみさんは「組み立てる人が作業しやすいよう工夫した。衣装修復の担当者と意思疎通を図りながら人形を修復するという、貴重な体験をさせていただいた」と振り返った。
29日は八戸市教育委員会が市民対象のお披露目会と、神社関係者向けに人形・衣装の取り扱いを学ぶ講習会を開いた。市社会教育課の柏井容子主査兼学芸員は「多くの事業費と時間をかけて修復された。丁寧に取り扱ってほしい」と呼びかけた。